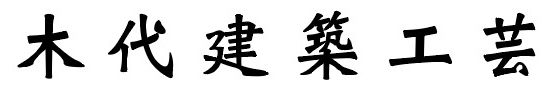宮大工の世界で広く知られる「鵤工舎」
小川三夫氏に弟子入りした職人たちは、どのような日々を過ごし、何を学んだのか。
鵤公舎で修業を経験し、現在は建設業を経営されてる「木代建築工芸」高橋代表に、Q&A方式でお話を伺いました。
修業時代について
Q1. 鵤工舎での修業を志したきっかけは何でしたか?
当時はNHKのプロジェクトXなどで鵤工舎の存在を知りました。法隆寺の1400年の伝統の技術を体験したかった。本物、最高峰の技術を体験したかった。それがきっかけとなります。
弟子入の応募をしましたが、すぐには叶わずでした。ある日に突然、小川三夫さんから電話を頂いて弟子入りすることが出来ました。
Q2. 実際に修業を始めて、最も驚いたことや印象的だった出来事は?
「弟子たちの熱心さ」「空気感」ですかね。
仕事や修行の時間は朝の8時から5時まででしたが、その間のパフォーマンスを高める為に皆が常に考えてました。他の時間は自主的に道具の手入れや練習をおこなってました。高度な領域に到達するための集団という雰囲気が印象に残ってます。
Q3. 日々の生活やスケジュールはどのようなものでしたか?
仕事や修行の時間は、朝8時から夕5時まで、休みは日曜日でした。それ以外の時間は自主的に道具の手入れや、修練をしてます。寝るとき以外は修行って感じです。ただ自分は日曜日は休んでました。日曜日も修練を続ける人もいました。
Q4. 技術以外に学んだこと(礼儀、精神性、哲学など)はありますか?
今の時代に逆行するかもしれませんが、職人は仕事時間外の段取りや準備も大事でしょうか。
Q5. 修業中に特に心に残っている教えや言葉はありますか?
修行の終わりあたりに、小川三夫さんに「宮大工として独立するのは厳しいぞ」って言われた事です。よく覚えています。私は独立するつもりでした。実際に経営されてる小川さんの言葉で重みがあります。私も独立して厳しい時期を経験しました。
Q6. 一番苦しかったことは? どうやって乗り越えましたか?
目標を持つ事でしょうか。目標がなかったら潰れると思います。高すぎる目標でも潰れる。富士山の登山で例えると頂上じゃなく、1合目、2合目の小分けにした目標を持つ事です。とりあえず小さな目標をなんとか乗り越えていきました。
Q7. 鵤工舎で身についた「一生モノの習慣」あれば教えてください。
「日報をつける」です。数日まとめて付ける時もあるけど、今でも続けてます。
Q8. 弟子同士の関係性はどうでしたか?競争?協力?
基本は協力であります。跡目争いや一子相伝ではなかったです。ただ、近い実力の人は意識してライバルとしてよき競争があったように思えます。
Q9. 小川三夫氏から直接受けた教えで、今も守っていることは?
小川氏から直接指導は特にありませんでした。上記の日報は今でも守ってます。
Q10. 外からは分かりにくいけれど、中に入って初めて分かったことは?
宮大工になりきれる人が思った以上に少なかったです。100人に一人くらいの感じです。不器用だと難しいし、器用でも飽きる人もいました。
「木の扱い」は想像以上に難しかったです。自分は他の仕事はある程度は真似ができるけれど、「木の扱い」は簡単ではなかったように感じます。それと「大工」が中心に現場がまわるので「大工」には重い責任があります。
独立後・現在の活動について
Q11. 修業の経験は、現在の仕事にどのように活かされていますか?
お寺やお宮の修繕、ちょうさや太鼓の修繕などで活かせてます。太鼓は常に地震が起きてるようなものですから、木材の組み合わせや加工に高い技術が必要です。一般住宅ではそこまでの技術は求められないけれど、こういった下地があると応用できます。
Q12. 独立後、どのような家づくりや建築に取り組んでいますか?
店舗や普通の家を作ってます。古民家再生やリフォームなど時代に求められるモノを作っています。
Q13. 現代の建築と伝統技術をどう融合・共存させていますか?
どちらかというと「いいえ」です。時代が求めてないかもしれません。求められると応じる事はできます。今は、欄間の彫刻とかなくなりましたよね。
Q14. 鵤工舎で学んだ価値観を、施主さんにどう伝えていますか?
一般住宅の方には伝えてはないです。ただ下地にこういった経験や技術があります。
Q15. いま振り返って、修業期間をどう評価していますか?
もっとやれとったなと思うな。
Q16. 修業時代がなければ、今の自分はどうなっていたと思いますか?
とにかく修行はどこかでしたと思います。
人材育成・後進指導について
Q17. 今、ご自身で弟子を育てる立場ですか? その時に心がけていることは?
教える立場だった事もありますが、経営と両立させるのは難しいです。職人になれるかは結局は本人次第でしょうか。教えただけでは覚えなし、実践の場がないと上達しないです。あと大工は雑用仕事が少ないです。つまり教えるのに人手がかかります。いろいろ苦慮しています。
Q18. 鵤工舎での教えと、現代の若者への指導で違いを感じる部分はありますか?
現在は機械やマニュアルでだれでも、即戦力、同品質です。準備も片づけも会議も(飲み会も)労働時間とされます。時代とともに職人が育ちにくい環境へなりつつあると感じます。
Q19. 「伝える」ことの難しさと面白さを感じる場面は?
対人は難しいです。ほんまに難しいと感じてます。
Q20. 次の世代に伝えたいこと、残したい言葉は何ですか?
宮大工は大変だぞと。伝えたいです。好きじゃないと続かないと思います。さらに修行中は、技術がある一定のレベルに達しないと楽しくならないです。自分は経営者となり、木に向き合う時間が減りました。少し否定的な締めとなりましたが、どの業界でも、喜びと苦しみがあると思います。
おわりに
ご覧いただきましてありがとうございました。45分ほどの対談でした。現在「木代建築工芸」では宮大工修行の募集は行われてません。